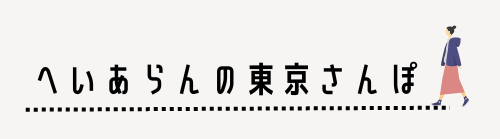ブラタモリは東大の赤門からスタート。
赤門は現在は閉じています。
耐震の問題で閉まっているのですが、これも貴重な姿です。
今日の案内人は、東京大学の 堀内 秀樹さん。
東京大学は、加賀藩邸の跡地に明治時代に建設された国立大学。一万人以上が学びます。
東大に加賀藩はどんな宝を残したのでしょう。
タモリさんがぶらぶら歩いて解き明かします。
赤門
赤門はなぜここに建てられたのでしょうか?
タモリさんは、赤門の屋根の上を双眼鏡で観察します。赤門には、三つ葉葵の家紋(徳川の家紋)が入った瓦が載っています。
一行は、家斉の娘のよう姫が前田家に嫁いだ様子を描いた絵を眺めます。将軍家の娘が嫁ぐ時には赤門を作ることになっていました。普通は嫁いだお姫様が亡くなると門を壊すことになっていましたが、姫は明治時代まで長生きしたため、この門はギリギリ壊されずに残ることになったのです。
太平洋戦争中も、東大の学生がバケツリレーで戦火から守ったため、赤門は今日まで残っています。
加賀藩邸が本郷にあった理由
加賀藩の屋敷はなぜ本郷にあったのでしょう?
一行は、東京大学農学部前の交差点に立ちます。
この交差点は、日光御成道と中山道が交わる交通の要衝で、江戸時代から商店街も広がっていた。
すでに町があるので、学生が過ごす町として発展しやすかったのです。
交差点にある老舗の酒屋「高崎屋」も画面に映りました。「酒屋も学生街には大事」トタモリさん。
周りに下り坂が多いので、本郷通りは台地の上を通っていることがわかります。加賀藩は台地の上に屋敷を構えており、借景として不忍池と上野の山も見えました。江戸城からもほどよい距離にあり、最高の立地。加賀藩のおかげで、東大は台地の上に広大なキャンパスを構えることができた。
三四郎池
一行は、いよいよ東大の構内に入ります。タモリさんは学生たちの声援を受けます。
「建物が落ち着いていますね」キャンパス内の建物はレンガ色のトーンで統一されています。
一行は、自然豊かな道に入ります。「これが三四郎池ですか。大学の中とは思えないね」
江戸時代から手つかずの三四郎池は、夏目漱石の『三四郎』に出てくることから名前がつきました。
前田家藩邸の絵図を見ると、実際の池は、今見えている以上に広いことがわかります。
前田家の庭園は、江戸時代の大名庭園随一といわれていました。池のそばまで来ると、ますます大名庭園らしい様子になります。
三四郎の中でも出てくる。学生は、静かな池の近くで考えをめぐらせ、アイデアがうまれます。
台地にある屋敷の中に三四郎はあるのはなぜでしょう?
台地の中でも、ここは段丘(より高い場所とより低い場所の境界)になっています。境界では水が出るため、谷頭浸食によって池ができました。高台であって池もあるという素晴らしい場所です。
三四郎池は、関東大震災時、火事にあった校舎の防火にも役立ちました。殿様も予想していなかったでしょう。
懐徳館(かいとくかん)庭園
明治時代になってからも前田家は宝は残しています。
「普段は入ることができない門の先に宝がある」と、特別に案内してもらいます。
懐徳館庭園は、明治時代の終わりに前田家が整備した庭園です。明治時代治になってからも、前田家は本郷に邸宅と庭園を構えて暮らしていました。1928年に本郷の土地を譲渡しましたが、「庭園は残してほしい」と管理費をつけて立ち去ったそう。
今は、海外の学長レベルのVIPの迎賓館として使われています。「外国の人は喜ぶでしょうね」
タモリさんの感想です。
「前田家の宝は守り継がれている。面白かったな。思った以上だね。」