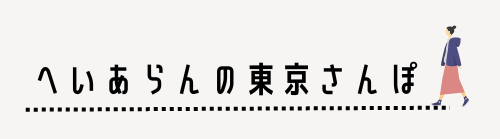青梅市にある塩船観音寺のつつじを見に行きました。
約20種、2万本のつつじが、境内を取り巻く丘に植えられています。境内から見上げても、上から眺めても、鮮やかなつつじの世界が広がります。仁王門や阿弥陀堂は、室町時代のもので、国指定重要文化財。茅葺の屋根が素敵です。
青梅線の東青梅駅・河辺駅から、2km少々と距離はありますが、一見の価値ありです。

この記事では、塩船観音寺のつつじについて
・見頃時期
・アクセス
・見どころ
などについてまとめました。
塩船観音寺のつつじ 見頃時期・開花情報
塩船観音寺は、ホームページで、つつじの開花情報を発信しています。開花時期は、2日に1回くらいのペースで、定点から撮影した写真や、開花している品種についての情報を更新しています。大変わかりやすいので、おでかけ前にぜひごらんください。
塩船観音寺ホームページの2025年 つつじ開花情報
・4月17日
早咲きのヤマツツジ系のオレンジ色が多くなってきました。
・4月21日
早咲きのヤマツツジが最盛期。中咲きのクルメ、キリシマツツジの蕾も膨らむ。
・4月23日
早咲きのヤマツツジから中咲きの赤いクルメツツジ・キリシマツツジにきりかわる。
・4月25日
見頃がきました。中咲きの赤いツツジと遅咲きの蕾がコラボ。
・4月27日
早咲きは終了。護摩堂左側も色が濃くなり全山色付きました
・5月1日~
主役は遅咲きの蕾が開いたオオキリシマ、リュウキュウツツジに。
・5月6日
本日をもちまして令和7年塩船観音寺つつじまつりは終了といたします。
6月上旬にはツツジは丸く刈り込まれます。
塩船観音寺で配られている「塩船観音寺つつじまつり」のチラシには、代表的なつつじの例年の開花時期が記載されていました。
| ミツバツツジ | 4月上旬~中旬 |
| オオヤマツツジ | 4月中旬 |
| ヤマツツジ | 4月中旬~下旬 |
| キシツツジ系 若鷺 | 4月中旬~下旬 |
| キリシマツツジ系 霧島 | 4月下旬~5月上旬 |
| クルメツツジ系 小蝶の舞 | 4月下旬~5月上旬 |
| キリシマツツジ系 日の出 | 4月下旬~5月上旬 |
| 江戸キリシマツツジ系 東錦 | 5月上旬 |
| リュウキュウツツジ系 濃紫 | 4月下旬~5月上旬 |
| オオキリシマ系ツツジ 曙 | 4月下旬~5月上旬 |
| リュウキュウツツジ系 琉球絞 | 5月上旬~ |
| リュウキュウツツジ系 関寺 | 5月上旬~ |
多くの品種のあるつつじ園なので、長い間つつじの花を楽しめるようです。令和7年は4月25日から見頃にはいり、5月1日現在、遅咲きのつつじが開花しています。
私は2025年5月3日 の午前中に訪問しました。最盛期の終盤でしたが、遅咲きのつつじが多く咲いていて、美しい景色を楽しみました。
塩船観音寺へのアクセス
塩船観音寺へのアクセスは次のようになります。
・JR「河辺駅」より徒歩40分
・JR「河辺駅」よりバス「塩船観音入口」徒歩10分
・JR「東青梅駅」より徒歩30分
・JR「東青梅駅」よりバス「塩船観音入口」徒歩10分
東青梅駅からのアクセス

私が撮った写真で、東青梅駅から塩船観音入口までのルートをご案内します。
結構距離があるので、バスで「塩船観音入口」から向かう方が多いようでした。

東青梅駅北口から、北二向かって歩きます。

このあとは、「塩船観音寺」の矢印に沿って進みます。

このような道を東に進みます。

再び、塩船観音寺の矢印看板があったので、左折します。
写真に写っているお堂は「青梅六万薬師」。
この地にあった「師岡城」が落城した際に戦死した人たちを弔い、 その後起こった飢饉や悪疫の流行を除くために、根ヶ布天寧寺八世の正翁長達和尚が法華経六万部を読誦。薬師如来像を招来して薬師 堂を建てたのだそうです。
ここからは、「市役所六万通り」を歩いて行きます。

前方には緑の丘が見えてきました。
東青梅駅前には、多くの観光客の姿がありましたが、歩いている人はぽつりぽつり。塩船観音寺を目指しているように見えました。

霞川を渡ります。

突当りには「光明寺」がありました。

ここには「勝沼城跡」の看板が立っていました。
・三田氏の居城であったが、15世紀に北条氏に滅ぼされた。
・その後、北条の家臣師岡氏が入ったたため「師岡城」とも呼ばれる。
・16世紀末、八王子城落城とともに廃城になった。
・曲輪、堀、土塁が良好に保存されていて、見学もできる。
思いがけない城跡の登場にわくわく。

光明寺の前の道を東に向かいます。

「東青梅六丁目東」の信号を左に。「城山通り」を進みます。

「城山通り」を左手に丘陵を見ながら進みます。ガードレールがない部分もあって、車通りも多いので注意が必要です。

「塩船観音寺」の看板が出てきたので、左折します。
城山通りにはバスが通っていて、このあたりまでバスで来ることができます。

道は段々と登り坂になりました。

坂はややきついですが、緑一杯の中を進みます。

塩船観音寺近くまで来ると、駐車場への案内の方が何人も誘導をしていました。

着きました。東青梅駅から30分程。遠いですが、史跡あり、山道ありで、変化に富んだコースでした。
塩船観音寺のつつじの見どころ

塩船観音寺のつつじを私が撮影した写真でご案内します

入口の仁王門は茅葺きで、室町時代に作られたと推定されています。

仁王像は、鎌倉時代に定快によって作られたと考えられています。

つつじまつりののぼりが並ぶ参道を通って、阿弥陀堂に向かいます。このあたりは、かなり混みあっていました。

塩船観音寺では、つつじまつり期間のみ、入山料が必要になります。大人300円です。
入山券売り場は、少しだけ並びました。

本堂までは、階段を上ります。
階段の下には、地元野菜や焼き立てメロンパンのお店が出ていました。

本堂でお参り。こちらはあまり混んでいなくて、落ち着いてお参りできました、本堂のそばには、地域の名産品を売る売店がにぎわっていました。
本堂から左の方に歩いて行くと、つつじの絶景が見えてきました。

写真正面に映っている建物「弘誓閣護摩堂」の周囲は、すり鉢状に斜面に囲まれています。 斜面にはヤマツツジが自生していましたが、昭和41年からつつじの植栽がはじまり、現在では約20種類約20000本のつつじが植えられています。平成22年には、つつじ園山頂に「塩船平和観音」がつくられました。
この日の「弘誓閣護摩堂」前には、たくさんの人が集まっていました。つつじの開花時期に行われる「塩船観音つつじまつり」期間中には、さまざまな行事が行われます。
訪問した5月2日には、「大護摩火渡り荒行」が11時から行われるとのことでした。一般の人も参加できるそうです。

つつじ園入口右側は、枯れてしまったつつじも多かったのですが・・

他の斜面に目を向けると、まだまだ咲いています。

山頂の「塩船平和観音」を目指して、丘を上がっていきます。つつじ園内には、舗装された比較的広い道の他、写真のような細い道があります。ここまで来ると、混雑はまったく気になりません。


開花したばかりの美しいつつじが沢山。前日の雨でぬれていて、それがまた美しい姿でした。まだつぼみもあって、しばらく楽しめそうです。


だいぶ高いところまで上がってきました!

頂上の観音像の周りは展望台になっています。遠くまで見渡せて、絶景でした。

広い道を通って、丘を降ります。ベンチも所々に置かれています。

振り返ると、つつつじの向こうに観音像が。

[
「招福の鐘」が見えてきました。参拝者が鐘をつくことができるとあって、鐘の音が響いていました。この音がつつじを見ている間中ひびいていて、それがまたよかったです。

「弘誓閣護摩堂」前の広場に降りてきました。「信徒会館普門閣」の前には、いくつかのテントがあって、団子やスイーツを売っていました。
私は、「ふじみや」のテントで焼きド―ナツを購入。これができたてのようで、とても美味でした。「信徒会館普門閣」内では、ソフトクリームや麺類なども販売していて、中のテーブルで食べることができるようになっていました。地元産のこんにゃくや漬物なども売っていました。
塩船観音寺。食べる楽しみも多いお寺でした。
塩船観音寺の歴史と概要
塩船観音寺の歴史と概要は以下のとおりです。
・大化年間(645~650年)に若狭の国の八百比丘尼が観音像を安置したのが開山と伝えられる。
・天平年間(729~749年)に僧行基菩薩が、周囲が小丘に囲まれ船の形に似ていることから、仏が衆生を救おうとする願いの船である「弘誓の舟」になぞらえて「塩船」と名づけたと言われる。
・八百比丘尼にあやかって、不老長寿の観音様、馬の守り神として信仰された。現在でも。家内安全・厄除け・交通安全などの観音様として信仰される。
・春のつつじの他、夏の紫陽花・山百合、秋の彼岸花・萩と、四季の花が美しい寺として知られている。
塩船観音寺のつつじ まとめ
青梅市にある塩船観音寺のつつじを見に行きました。
約20種、2万本のつつじが、境内を取り巻く丘に植えられています。境内から見上げても、上から眺めても、鮮やかなつつじの世界が広がります。仁王門や阿弥陀堂は、室町時代のもので、国指定重要文化財。茅葺の屋根が素敵です。
青梅線の東青梅駅・河辺駅から、2km少々と距離はありますが、一見の価値ありです。